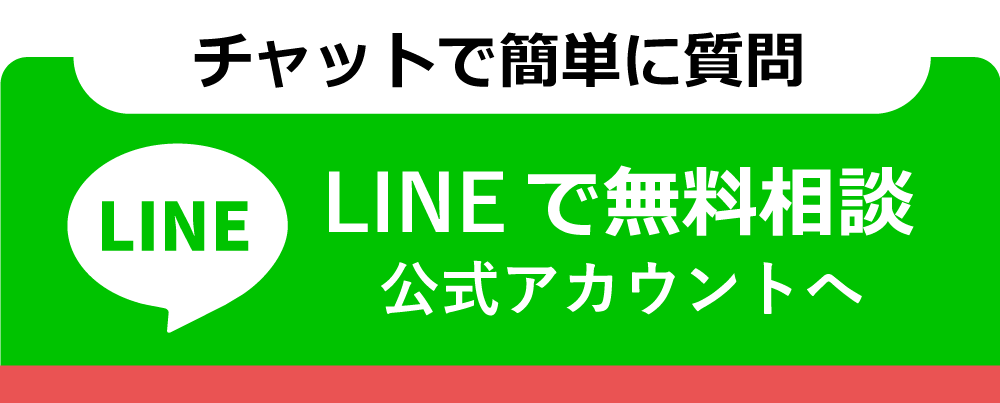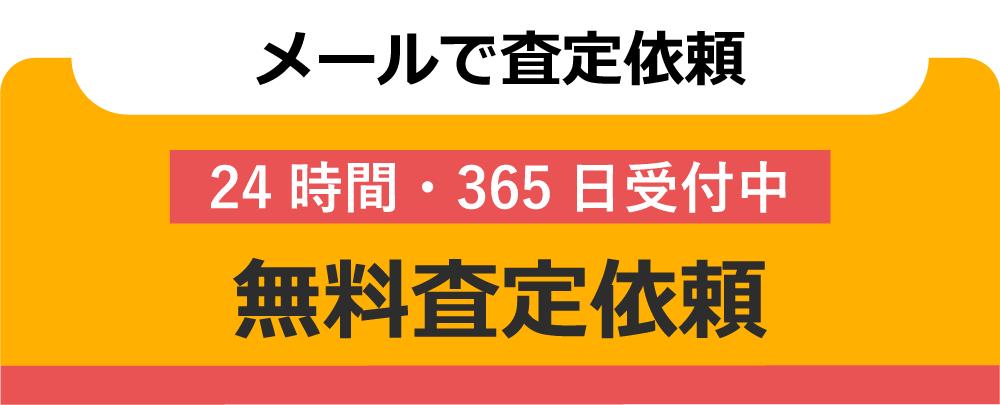著者:熊本不動産買取センター

「不動産を相続したものの、『売却した方がいいのか』『登記や税金の手続きが複雑そう』と悩んでいませんか?【2025年】には不動産登記法が大きく改正され、相続登記が義務化されることで、正当な名義変更を怠ると10万円以下の過料が科されるリスクが現実になります。また、相続した土地を国に帰属できる「相続土地国庫帰属制度」も始まり、要件や手続きのハードルが上がっています。
さらに、相続不動産を【3年以内】に売却すれば、譲渡所得税の取得費加算特例や特別控除など大きな節税メリットが受けられる一方、申告や必要書類の準備を怠ると数十万円単位で損失が発生することも少なくありません。実際、相続手続きを放置したことで固定資産税や管理費用が累積し、想定以上の出費に悩む方が増えています。
最新の法改正や地域別の市場動向まで丁寧に解説し、実際のシミュレーションや失敗例も交えながら、「今」知っておくべき売却戦略とリスク対策を網羅します。
「複雑な手続きをどう進めればいい?」「税金の控除を最大限に活用したい!」——そんな不安や疑問をスッキリ解消したい方は、ぜひ続きもご覧ください。」
スムーズで安心の不動産売却をサポートします – 熊本不動産買取センター
熊本不動産買取センターでは、不動産売却に関するお悩みに真摯に対応し安心・迅速な取引をサポートいたします。仲介ではなく直接買取に特化することで、仲介手数料不要・即現金化・瑕疵担保責任なしなど、売主様にとって負担の少ないお取引を実現しております。戸建て・マンション・土地など、あらゆる不動産に対応可能です。売却を急がれる方や相続・空き家などのお悩みをお持ちの方もぜひ熊本不動産買取センターにご相談ください。安心してお任せいただける体制を整えておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2025年最新の不動産相続制度の改正ポイントと影響
2025年の法改正により、不動産の相続に関する手続きや義務が大きく見直されました。特に相続登記の義務化や国庫帰属制度の導入など、相続人にとって重要な変更点が多く含まれています。これにより、相続した土地や建物の管理や売却の流れ、税金対策にも影響が及びます。
2025年改正不動産登記法の概要と適用範囲
不動産登記法の改正では、相続による所有権移転登記が義務となり、期限内に手続きを行わない場合は過料の対象となります。適用範囲は全国の土地・建物すべてで、個人・法人問わず相続人全員に適用されます。従来は任意だった登記が義務化されることで、不動産の名義が長期間変更されない「所有者不明土地」問題の解消が期待されています。
相続登記義務化の期限・罰則・対象者について詳述
| 項目 | 内容 |
|---|
| 期限 | 相続発生を知った日から3年以内 |
| 罰則 | 正当な理由なく期限を超過した場合は10万円以下の過料 |
| 対象者 | 土地・建物を相続したすべての相続人 |
| 必要書類 | 戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産権利証ほか |
ポイント
- 相続登記が義務化されたため、早めの手続きが重要です。
- 期限を過ぎると過料が科されるリスクがあります。
- 複数人で相続した場合は全員が手続きの対象となります。
国庫帰属制度の利用条件と注意点
新たに導入された相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。すべての土地が対象になるわけではなく、厳格な条件があります。
| 利用条件 | 内容 |
|---|
| 対象不動産 | 管理不全や瑕疵のない土地 |
| 除外物件 | 建物付き、担保権設定済み、境界未確定等 |
| 手数料 | 原則1筆20万円程度 |
| 申請手続き | 書類提出と現地調査 |
注意点
- 建物が残っている、土壌汚染のある土地は対象外です。
- 手数料や除去費用の負担が発生する場合があります。
相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリットを具体的に解説
メリット
- 不要な土地の管理・固定資産税の負担から解放されます。
- 相続人間のトラブル回避につながります。
デメリット
- 申請に手数料がかかり、すべての土地が対象とはなりません。
- 土地の状況や権利関係により申請が却下される可能性もあります。
2025年以降の制度変更による売却手続きへの影響
改正により、相続による不動産売却には厳格な登記義務が課され、未登記だと売却ができなくなります。売却前に登記を済ませていない場合、買主が見つかっても契約締結や引渡しが進まないリスクが発生します。税金面でも、相続から3年以内の売却は特例控除が適用される場合があるため、売却タイミングの見極めが重要です。
登記義務化による売却準備の重要性とリスク回避策
売却準備で押さえるべきポイント
- 相続登記の早期完了 売却手続きや価格査定をスムーズに進めるには、名義変更を済ませておくことが必須です。
- 必要書類の事前準備 戸籍、遺産分割協議書、不動産権利証などを揃えておくことで、売却の遅延を防げます。
- 税金・特例の確認 3年以内売却の特例や譲渡所得税の控除など、活用できる優遇措置を事前に確認しましょう。
リスク回避策
- 早めの専門家相談で手続きミスや罰則リスクを防ぎましょう。
- 複数の相続人がいる場合は、全員の意思確認と協力が不可欠です。
不動産相続制度の改正は、売却や管理に大きな影響を与えます。新制度を正しく理解し、早めの行動でトラブルや余計な負担を回避することが大切です。
相続した不動産の売却タイミングと最適戦略
相続した不動産の売却は、タイミングによって税金や手続きの負担が大きく変わります。特に相続後3年以内に売却することで得られる特例や控除があり、計画的な売却戦略が重要です。売却時には、相続登記や必要書類の準備、税務上の優遇措置など、いくつかの重要なポイントを押さえることで損を防げます。
相続後3年以内に売却すべき理由と税務メリット
相続不動産を3年以内に売却すると、税金面で大きなメリットがあります。主な理由は「取得費加算の特例」と「空き家の控除」などの優遇制度が利用できるためです。
以下のテーブルで主な税務メリットを整理します。
| 特例・控除 | 条件 | 内容・メリット |
|---|
| 取得費加算の特例 | 相続発生から3年以内の売却 | 相続税の一部を取得費に加算でき譲渡所得税が軽減 |
| 空き家の控除 | 一定条件を満たす空き家の売却 | 譲渡所得から一定金額を可能 |
強調ポイント:
- 3年以内の売却で相続税額を取得費に加算できるため、譲渡所得税の課税額が減少します。
- 空き家特例を利用すれば、売却益の多くが非課税となるケースもあります。
3年以内売却による取得費加算特例、譲渡所得税軽減の仕組み
取得費加算の特例は、相続で取得した不動産を相続開始日から3年以内に売却した場合、相続税のうち不動産にかかった分を取得費として加算できる制度です。これにより譲渡所得が少なく計算され、結果として譲渡所得税を抑えることができます。空き家の控除は、被相続人が一人暮らしであった住宅に適用され、売却益から一定額を差し引けるため、実質的な税負担が大きく減ります。
生前売却と相続後売却の比較とメリット・デメリット
不動産を売却するタイミングは「生前」と「相続後」で大きく異なります。それぞれのメリット・デメリットを整理します。
| 項目 | 生前売却のメリット | 相続後売却のメリット |
|---|
| 節税効果 | 固定資産税や管理費の軽減 | 取得費加算特例・控除適用 |
| 手続きの簡易さ | 売却手続きがシンプル | 相続人全員の合意で売却可能 |
| 注意点 | 贈与税が発生する場合がある | 相続登記・名義変更が必要 |
ポイント:
- 生前売却は贈与税に注意が必要ですが、相続税対策や不動産管理の手間軽減につながります。
- 相続後の売却は税制優遇が受けられますが、登記や遺産分割協議が必要になるため慎重な手続きが求められます。
相続前売却の節税効果と相続後売却の注意点を具体的に整理
相続前に売却すると、不動産の管理負担や将来的な相続トラブルを回避できる点が大きな利点です。ただし、所有権移転時に贈与税が発生するケースがあるため、事前に費用計算を行いましょう。相続後に売却する場合は、相続登記や遺産分割協議が必須です。不動産の名義変更や相続税の申告も必要になるため、専門家への相談が有効です。
地域別の市場動向と売却のポイント
不動産の売却価格や成約スピードは、地域の市場動向によって大きく異なります。名古屋市や渋谷、港区、葛飾区、江戸川区などでは、それぞれのエリア特性を把握した売却戦略が重要です。
名古屋市、渋谷、港区、葛飾区、江戸川区の特徴を踏まえた売却戦略
| 地域 | 特徴 | 売却戦略のポイント |
|---|
| 名古屋市 | ファミリー層に人気、交通利便性 | 住宅需要が高い時期に売却を検討 |
| 渋谷 | 商業地・高価格帯 | 事業用・投資用としての提案が有効 |
| 港区 | 高級住宅地、外国人需要 | 海外投資家向けのPRも効果的 |
| 葛飾区 | 下町情緒、地元需要が安定 | 相続物件としての需要を強調 |
| 江戸川区 | 子育て世帯が多い | 学区や生活環境をアピール |
ポイント:
- 地域ごとの市場動向を把握した上で、物件の魅力やターゲット層に合わせた売却活動が効果的です。
- 地域特有の税制優遇や助成金がある場合もあるため、地元の不動産会社や専門家への相談をおすすめします。
相続不動産売却に必要な手続きと書類完全ガイド
相続した不動産を売却する際は、正しい手続きと必要書類の準備が不可欠です。特に2024年から相続登記が義務化され、手続きを怠ると過料の対象になるため注意が必要です。売却の流れや申告方法、各書類の取得方法まで、具体的に解説します。
相続登記の具体的な手順と義務化対応
相続登記は不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する重要な手続きです。義務化により、相続を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
以下の表に主な必要書類と費用、手続きの流れをまとめました。
| 必要書類 | 取得先 | 主なポイント |
|---|
| 被相続人の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 出生から死亡まで全て必要 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 続柄確認のため |
| 遺産分割協議書 | 作成(相続人) | 全員の実印・印鑑証明書要 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | 登録免許税計算に利用 |
| 登記申請書 | 法務局 | 司法書士依頼も可能 |
司法書士へ依頼する場合の費用は10万円~20万円が目安です。手続きの正確性や時間短縮の面でも、専門家の活用が推奨されます。
売却に必要な書類一覧と取得方法
不動産売却には登記関連以外にも複数の書類が必要となります。以下のリストを参考に、抜け漏れなく準備しましょう。
- 登記簿謄本(登記事項証明書):法務局で取得
- 固定資産評価証明書:市区町村役場で取得
- 身分証明書:運転免許証やマイナンバーカード
- 印鑑証明書:市区町村役場で取得、有効期限注意
- 遺産分割協議書:相続人全員の記名・押印が必要
- 戸籍謄本・除籍謄本:相続関係説明用
これらの書類は、不動産会社や買主との売買契約時、所有権移転登記、税務申告など複数の場面で必要となります。特に評価証明書や印鑑証明書は発行日から3ヶ月以内のものが求められる場合が多いため、取得タイミングに注意しましょう。
確定申告時に必要な書類と注意点
相続不動産を売却した場合は、翌年の確定申告で譲渡所得の申告が必要です。主な必要書類とポイントは以下の通りです。
- 譲渡所得申告書(申告書B)
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書
- 取得費を証明する書類(相続時の評価、購入時の契約書等)
- 譲渡費用の領収書(仲介手数料など)
- 住民票や印鑑証明書
申告期限は売却した翌年の2月16日から3月15日です。譲渡所得の計算時は「取得費加算」や「特別控除」など、適用できる特例を必ず確認しましょう。
必要書類に不備があると控除が受けられない場合もあるため、早めの準備と専門家への相談がおすすめです。特に取得費が不明な場合や空き家特例の適用希望時は、追加の証明書類が必要になる点にも注意してください。
相続不動産売却にかかる税金・控除・特例の全貌
相続した不動産を売却する場合、税金や各種控除、特例の適用条件をしっかり理解することが重要です。特に譲渡所得税や相続税、さらに特別控除や空き家特例など、複数の制度が複雑に絡み合います。正しい知識がなければ、余計な税負担やトラブルの原因となるため、各制度の内容や計算方法、適用条件を具体的に確認しましょう。
相続税と譲渡所得税の違いと計算方法
相続した不動産を売却する際には、主に「相続税」と「譲渡所得税」の2つの税金が関わります。相続税は遺産を取得したときに課され、譲渡所得税は実際に不動産を売却した際の利益に対して課税されます。
下記の表で両者の違いを整理します。
| 税の種類 | 課税タイミング | 課税対象 | 計算方法・ポイント |
|---|
| 相続税 | 相続発生時 | 取得した遺産の評価額 | 遺産総額-基礎控除=課税対象額 |
| 譲渡所得税 | 不動産売却時 | 売却益(譲渡所得) | 売却価格-取得費-諸経費=譲渡所得 |
取得費の引継ぎ、譲渡所得の計算式、税率の説明
相続した不動産を売却する場合、取得費は被相続人(前所有者)の取得費を引き継ぐ形となります。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなすことも可能です。
譲渡所得は以下の式で計算されます。
- 譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
- 譲渡所得税=譲渡所得×税率(所得税+住民税)
税率は所有期間によって異なり、相続開始日から売却日までが5年超なら「長期譲渡所得」として約20%、5年以下なら「短期譲渡所得」として約39%が課されます。
特別控除の要件と適用手続き
相続した不動産を売却する際、「居住用財産の特別控除」が適用できるケースがあります。これは、譲渡所得から一定金額を控除できる制度で、税負担の軽減に大きく役立ちます。
適用要件の主なポイントをリストにまとめます。
- 被相続人が居住していた家屋またはその土地であること
- 相続開始から3年以内に売却すること
- 売却時点で空き家である、または一定の条件を満たすこと
- 相続人が過去に同じ特例を適用していないこと
申請手続きは確定申告時に必要書類を添付し、税務署に提出します。
適用対象住居の条件、控除額の具体的計算例
控除対象となる住居の条件は以下の通りです。
| 条件 | 内容 |
|---|
| 居住の事実 | 被相続人が直前まで居住していたこと |
| 空き家期間 | 相続後に空き家で売却されること |
| 建物の要件 | 昭和56年5月31日以前の建築(耐震基準未適合可) |
| 過去の利用 | 相続人自身が過去に同特例を利用していないこと |
空き家の控除特例と利用時の注意点
空き家の控除特例とは、相続した「空き家」を一定条件で売却した場合に譲渡所得から一定金額を控除できる制度です。空き家問題の解消を目的として導入されています。
主な対象・非対象、注意点をリストで整理します。
- 対象:被相続人が一人暮らしで住んでいた家屋、相続後に住む人がいない
- 非対象:共有名義や賃貸中、法人所有の不動産
- 申請には「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類が必要
- 期限:相続開始から3年以内に売却契約を締結すること
申請方法は、確定申告時に必要書類をそろえて税務署に提出します。
注意点は、複数の相続人がいる場合は分割協議が整っていること、また「空き家」と認められる条件を満たすか事前に自治体へ確認することが大切です。
この特例を利用することで、余計な税負担を減らし、スムーズな相続不動産売却が可能となります。
相続不動産売却のメリット・リスクと失敗しないための注意点
売却しない場合の維持コストやリスク
相続した不動産を売却せずに保有し続ける場合、さまざまなコストやリスクが発生します。特に問題となるのが、固定資産税や管理費の継続的な負担、老朽化による倒壊リスク、空き家状態による近隣トラブルです。以下の表で代表的なリスクとコストをまとめます。
| 項目 | 内容 | 発生例 |
|---|
| 固定資産税 | 毎年課税される | 建物・土地ごとに税額発生 |
| 管理費用 | 草刈り・修繕など | 空き家巡回・修繕対応 |
| 倒壊リスク | 老朽化で倒壊・損壊 | 強風・地震などで被害拡大 |
| 近隣トラブル | 雑草・害虫・不審者 | 苦情・損害賠償リスク |
空き家状態が続くと「特定空き家」に指定され、行政から指導や固定資産税の増額対象になる場合もあるため、注意が必要です。
相続人間でのトラブル事例と防止策
相続した不動産の売却を巡っては、相続人間の意見の食い違いによるトラブルが頻発します。特に、遺産分割協議がまとまらない場合や、名義変更が未了の場合は、売却手続きを進められません。
主なトラブル例
- 共有名義のまま売却が進まず、資産運用が滞る
- 分割方法や売却代金の配分で対立
防止策リスト
- 必ず全相続人で遺産分割協議書を作成し、合意内容を書面化する
- 法律上必要な手続き(相続登記、名義変更)を速やかに完了させる
- 意見がまとまらない場合は、専門家に早めに相談する
遺産分割協議の早期実施と法的手続きを怠らないことが、トラブル防止の最重要ポイントです。
特例や控除の申請忘れによる税負担増加リスク
相続不動産を売却する際は、特別控除や空き家特例などの優遇措置が受けられる場合があります。しかし、これらの特例や控除の申請を忘れると、本来よりも多くの税金を支払うことになってしまいます。
申請漏れの実例
- 3年以内の売却で控除を利用できたはずが、申請漏れで多額の譲渡所得税が発生
- 必要書類を揃えず確定申告時に控除が認められなかった
申告ミス防止のチェックリスト
- 必要な特例・控除の適用条件を事前に確認
- 必要書類(遺産分割協議書、登記簿謄本、確定申告書類など)を早めに準備
- 申告期限や手続きの流れを把握
- 不明点は税理士や専門家に確認
特例や控除の適用漏れを防ぐためには、事前の確認と適切な書類管理が不可欠です。
ケース別シミュレーションで理解する相続不動産売却の税務
単独相続・共有相続の場合の税負担比較
不動産を相続した場合、単独相続と共有相続で税金の計算や負担が異なります。単独で相続した場合は売却益に対する譲渡所得税や住民税を一人で負担しますが、複数人で共有相続した場合は、持分割合に応じて税金が分割されます。ただし、売却時の手続きや確定申告は各相続人ごとに必要となるため注意が必要です。
| 相続形態 | 譲渡所得税の課税方法 | 必要な手続き |
|---|
| 単独相続 | 全額を単独で計算・申告 | 登記、売買契約、申告1名分 |
| 共有相続 | 持分ごとに分割し計算・申告 | 持分ごとに登記・申告が必要 |
主な注意点:
- 単独相続の場合、全ての税負担・手続きを一人で行うため、進行がスムーズですが責任も大きいです。
- 共有相続の場合、税負担が分散する一方で、相続人間の協議や手続き調整が必要になります。
- 複数相続人がいる場合、譲渡所得税は各自で申告するため、取得費や控除の適用漏れに注意しましょう。
複数相続人がいるケースの税務上の違いを詳細に解説
複数の相続人が不動産を取得し売却する場合、各自の持分に応じて譲渡所得が計算されます。譲渡所得の計算式は下記の通りです。
- 売却価格(持分割合)- 取得費(持分割合)- 諸経費(持分割合)=譲渡所得
- 譲渡所得から各種控除を各自適用
各相続人ごとに確定申告が必要となり、必要書類や取得費の算定方法についても個別に確認することが重要です。共有名義の場合は、遺産分割協議書や登記手続きも慎重に進める必要があります。
相続不動産売却前後の戦略的プランニングと節税対策
相続した不動産を売却する際は、事前のプランニングが将来の税負担や手続きのスムーズさに直結します。不動産の売却時期や手順、税金の特例などを正しく理解し、最大限のメリットを得るための流れを確認しましょう。
- 相続前後で「売却に適したタイミング」を把握
- 税金や控除の仕組みを十分に理解
- 必要書類や申告手続きも早めに準備
相続不動産の売却は、土地や建物の所有者が変わる大きなイベントです。相続登記の完了、遺産分割協議、申告期限のチェックなど、複数の観点から計画的に進めることが重要です。
生前贈与を活用した節税対策のポイント
生前に不動産を贈与することで、将来の相続税や譲渡所得税の負担軽減が期待できます。しかし、贈与税や譲渡所得税の条件も確認が必要です。下記のようなメリット・注意点を押さえておきましょう。
| メリット | 注意点 |
|---|
| 相続税の課税対象財産を減らせる | 贈与税が発生する場合がある |
| 将来のトラブル防止に役立つ | 贈与後の売却は取得費に注意 |
| 贈与者が売却時の所得控除を活用可 | 贈与契約書など手続きが必要 |
生前贈与は、特例や控除の適用も視野に入れた慎重なプランニングが求められます。
控除を活用できる贈与・売却の組み合わせ
相続や贈与で取得した不動産を売却する際、「居住用財産の特別控除」が有効に使えるケースがあります。特に下記のような条件を満たす場合、控除を活用できます。
- 被相続人が一人で居住していた家屋・土地を売却する場合
- 相続開始から3年以内の売却
- 売却前に相続登記・名義変更が完了していること
この控除を利用すれば、譲渡所得から一定金額を差し引くことができ、大幅な税負担軽減となります。実際の適用可否や必要な書類は、事前に税理士や専門家に確認すると安心です。
相続後に売却する場合の節税特例と申告タイミング
相続後の不動産売却では、税金面での特例や申告スケジュールを押さえることが重要です。特に「取得費加算の特例」や「特別控除」などを適切に利用することで、納税額を抑えることが可能です。
- 相続税の申告期限は10か月以内
- 譲渡所得税は売却した翌年の確定申告で申告
- 特例の適用には各種書類と時期の条件を満たす必要あり
売却時期によっては、相続税額を譲渡所得から控除できるなどのメリットもあります。計画的な売却・申告が節税の鍵です。
取得費加算の条件と注意点
取得費加算の特例は、相続税を支払った場合にその一部を売却時の取得費へ加算できる仕組みです。適用条件や注意すべきポイントは下記の通りです。
- 相続開始から3年10か月以内に売却
- 売却資産が相続税の課税対象であること
- 相続税額のうち不動産に対応する部分のみ加算可能
この特例を利用することで、譲渡所得税の課税対象額を大きく減らすことができます。ただし、加算できる金額の計算や、必要書類の準備は複雑なため、早めの専門家相談がおすすめです。
相続せず売却する場合の手続きと注意点
不動産を相続せずに売却する方法には、遺産分割前の「換価分割」や、複数相続人での「共有名義売却」があります。どちらも法的な手続きや税務上の注意が必要です。
- 遺産分割協議で売却方針を全員合意
- 売却代金は相続人間で分割し、確定申告が必要
- 共有者全員の署名・押印が求められる場合が多い
売却後の所得税や分割方法、名義変更なども複雑になりがちです。スムーズな売却のためには、事前の話し合いと書類準備が不可欠です。
換価分割・共有名義の売却方法と法的注意事項
換価分割や共有名義での売却では、以下の点をしっかり確認しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 換価分割の条件 | 相続人全員の同意・遺産分割協議書の作成 |
| 共有名義売却の注意点 | 全員の同意・印鑑証明・名義変更手続き |
| 税務申告 | 売却益は各相続人がそれぞれ確定申告 |
| トラブル防止 | 書面での合意・専門家への相談が安全 |
名義や分割方法により手続きが異なるため、相続人間の十分な協議と法的なサポート体制が大切です。
不動産売却 相続に強い専門家選びとサービス活用法
専門家の選定基準と費用相場
相続した不動産の売却を成功させるためには、専門家選びが非常に重要です。税理士や司法書士、不動産会社の中でも相続案件に精通したプロを選ぶことで、手続きや税金対策、トラブル回避がスムーズに進みます。下記のテーブルは、不動産売却と相続に関わる主な専門家の特徴と費用相場をまとめたものです。
| 専門家 | 主な業務内容 | 費用目安(税抜) |
|---|
| 税理士 | 譲渡所得税の申告、取得費計算、節税 | 5万円~15万円 |
| 司法書士 | 相続登記、名義変更 | 3万円~10万円 |
| 不動産会社 | 査定、売却仲介、契約サポート | 売買価格の3%+6万円前後 |
| 行政書士 | 遺産分割協議書の作成 | 2万円~8万円 |
チェックすべきポイント
- 相続や不動産売却に関する実績や事例が豊富か
- 明確な料金体系と見積もりを提示してくれるか
- 相談時の対応や説明が丁寧で信頼できるか
これらを確認することで、安心して依頼できる専門家を選ぶことができます。
実際のサポート事例と成功体験の紹介
多くの方が「相続した土地を3年以内に売却」したケースで、税金の特例や控除をうまく活用し、納税額を大幅に抑えています。例えば、相続不動産の売却時に特別控除や空き家特例を適用できた事例では、必要な書類や手続きを専門家がサポートし、スムーズかつ安心して売却が完了しました。
依頼者の声
- 「相続登記から売却まで一括サポートで、煩雑さが解消しました」
- 「税理士に相談し、取得費や控除の計算を適切に行え、納税額を抑えられました」
- 「空き家特例の適用条件や必要書類について詳細に教えてもらい、確定申告もスムーズでした」
このように、専門家の適切なアドバイスとサポートが、成功体験につながるポイントです。
無料査定・相談サービスの活用ステップ
相続した不動産の売却を検討する際、まずは無料査定や相談サービスを活用するのが有効です。以下の流れで進めることで、売却までの不安や疑問を解消できます。
- 無料査定申込 信頼できる不動産会社や専門家のWEBサイトから、物件情報を入力して査定を依頼します。
- 現地調査と価格提示 担当者が現地を確認し、周辺相場や物件状態をもとに査定価格を提示します。
- 相談・提案 疑問や不安をしっかり相談し、売却方法や税金対策、必要書類についてアドバイスを受けます。
- 媒介契約の締結 納得できれば媒介契約を結び、売却活動をスタートします。
注意点
- 査定額だけでなく担当者の対応や説明内容もチェック
- 相談時には「相続した不動産の売却 確定申告」「取得費の証明方法」「特例の適用可否」など具体的に質問する
- 契約前に手数料やサービス内容を必ず確認する
無料サービスを賢く利用し、納得できる売却を目指しましょう。
div class=”info box”>
スムーズで安心の不動産売却をサポートします – 熊本不動産買取センター
スムーズで安心の不動産売却をサポートします – 熊本不動産買取センター
熊本不動産買取センターでは、不動産売却に関するお悩みに真摯に対応し安心・迅速な取引をサポートいたします。仲介ではなく直接買取に特化することで、仲介手数料不要・即現金化・瑕疵担保責任なしなど、売主様にとって負担の少ないお取引を実現しております。戸建て・マンション・土地など、あらゆる不動産に対応可能です。売却を急がれる方や相続・空き家などのお悩みをお持ちの方もぜひ熊本不動産買取センターにご相談ください。安心してお任せいただける体制を整えておりますので、お気軽にお問い合わせください。
会社概要
名称・・・熊本不動産買取センター
所在地・・・〒862-0920 熊本県熊本市東区月出2-5-37
電話番号・・・096-202-4620